介護施設での緊急時対応に自信はありますでしょうか?緊急時対応のマニュアルを作成している施設がほとんどだと思います。ですが実際に急変が起きた場合に、迷わず行動に移せる方ばかりではないでしょう。
介護施設における緊急時の対応には、事前の準備が欠かせません。急変に備え正しい知識と対応策を持つことが重要です。
今回は、緊急時における適切な対応や手順、事前に対策すべきことをわかりやすく解説していきます。緊急時にもスムーズな対応ができるようになりますので、是非参考にしてみてください。
覚えておきたい介護現場における緊急時の心得

介護施設で緊急事態が起きた時に、重要な事は「慌てず落ち着くこと」です。冷静に適切な判断ができなければ、事態を悪化させる可能性もあります。日頃から予測や準備することで、適切な対応ができるようになります。「あの時こうすれば良かった…」と後から後悔しないよう、心構えや手順を身につけ、確認事項を普段から把握しておきましょう。具体的な心得は以下のようになります。
- 慌てず冷静に対応する
- 安全な場所を確保する
- その場を離れず応援を呼ぶ
それぞれ順番に解説します。
慌てず冷静に対応する
介護の現場は、いつ、どこで、何が原因で緊急事態が起こるかわかりません。そんな時にパニックに陥り、慌ててしまうと冷静な判断ができません。また職員が慌てることで、急変者はさらに不安な気持ちや恐怖心が増大してしまいます。
冷静に対応するためには、あらゆる事態を想定し準備することが大切です。もしパニックになりそうな時は、深く深呼吸し自分を落ちつかせるとよいでしょう。
安全な場所を確保する
緊急時の対応として、安全な場所を確保することも重要です。不安定な場所で処置を続けてしまうと、適切な医療処置が難しくなります。また二次的な被害を引き起こしかねません。移動が難しい場合は、その場を安全な場に整えましょう。適切な環境で医療処置が行えるよう配慮が必要です。
その場を離れず応援を呼ぶ
急変時の対応として大切なことは、その場を離れず応援を呼ぶことです。状況の判断を一人で行うことは不可能であり危険な行為です。またその場を離れてしまうと、その間の状態変化を見逃してしまいます。発生時の状況を把握し、報告することがとても重要です。PHSの使用や大声で叫ぶなどし、他の職員を集めましょう。状況を共有し連携を図ることで、利用者の命を救うことにつながります。
情報を正確に伝えるためには伝え方が重要です。発見までの経緯、要点をまとめ、記録を付けるときは「〇〇だ」「〇〇である」調でまとめるとよいでしょう。
- だれが
- いつ
- どこで
- どうしたのか
- どうしてほしいのか
- 呼吸は、意識レベルは
などの情報を分かりやすい順序で提供しながら対応を仰ぎます。
スムーズな連携を達成するために、より良いチーム医療を構築するポイントです。普段から職員同士の信頼関係を築くことが求められます。
介護現場における緊急時の事前対策5か条
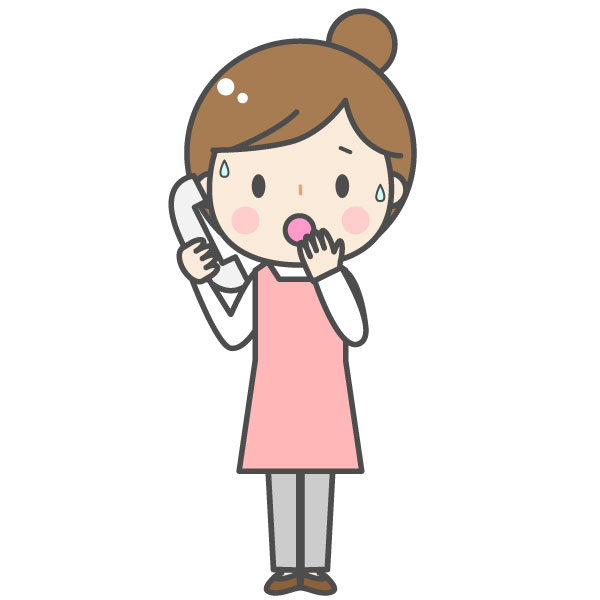
介護現場における緊急時の事前対策5か条は次の通りです。
- 備品の場所を把握
- 緊急マニュアルを確認
- 普段から急変をイメージしておく
- 積極的に勉強会や研修に参加する
- 日ごろから利用者をよく知っておく
それぞれ順番に解説します。
備品の場所を把握
緊急事に備え、備品の場所を事前に把握しておくことも重要です。いざ使用する時にパニックにならない為にも、AEDや背板がどこに設置されているか確認しておくとよいでしょう。
嘔吐時には感染対策グッズをさっと取りやすくまとめておくと便利です。また、簡易ベッドや(使用方法も確認しておく)PHSなど通信機器の使用訓練、ベッド柵の動作確認なども事前に行っておきましょう。
緊急マニュアルを確認
各施設に作成されているマニュアルに沿って対応することが基本です。前もってマニュアルを確認しておくことで、慌てず適切な対応が取れるようになります。また、マニュアルの保管場所も把握しておきましょう。いざという時は頭が真っ白になることも考えられます。そんな時はマニュアルを見ながら対応すれば良いので、マニュアルの保管場所だけでも念頭におき、すぐ分かるようにしておきましょう。
普段から急変をイメージしておく
介護施設において、適切な対応を実施するためには、日頃から急変時をイメージしておくことも忘れてはいけません。イメージを持てずにいると、いざその場面に直面しても、何をしたらよいのか分からず立ち尽くしてしまいます。「もし今、緊急事態が起きたらどうすればよいか」「今、急変したら、人を呼んであのスペースで対応しよう」など、急変時を想定することを習慣化するとよいでしょう。急変対応に関する知識や技術を身につけるとともに、意識的にイメージすることが大切です。
積極的に勉強会や研修に参加する
介護の現場で安心して業務に取り組むためには、積極的に学び続ける姿勢が大切です。周りの習慣に合わせ曖昧な認識のままにしておくと、誤った対応になり危険です。また、利用者の急変時にうまく対応できるか不安の状態で仕事を続けると、苦手意識が増大し、ストレスも増大してしまいます。不得意とすることを克服する為にも、研修会に参加するなど学びを続けることで、知識が増え自信につながります。
急変時の具体例は、利用者ごとに異なります。様々な状況に対応できるよう、学習の習慣を身につけましょう。
日ごろから利用者をよく知っておく
利用者の急な体調変化に備えるためには、普段の様子を把握しておくことが大切です。理由は、いつもの様子を知っているからこそ、異変に気づけるからです。「いつもと顔色が違う」「好きなものを残している」「いつもより握り返す力が弱い」など普段との「違和感」を感じることで、早期発見につながります。症状が軽い状態でも違和感を感じたら、注意深く観察を続けましょう。普段から利用者の健康状態はもちろん、趣味や嗜好、健康状態に関心をもつことも重要です。
まとめ
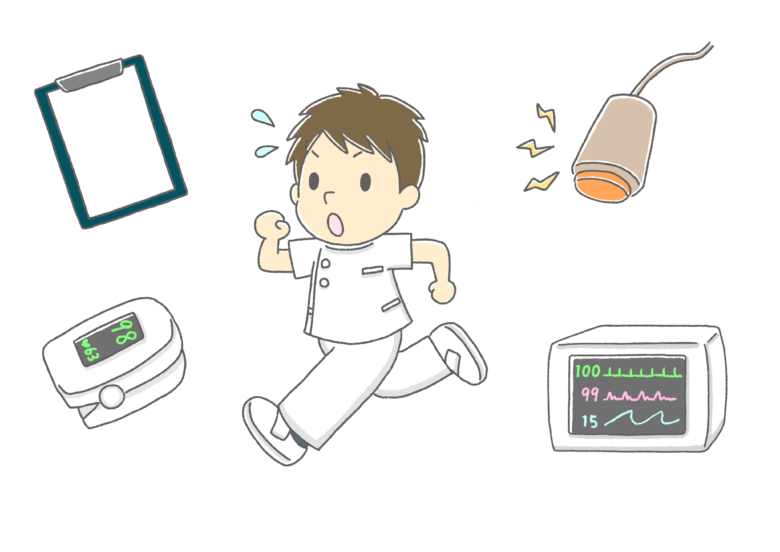
介護施設における緊急時には、慌てず冷静に判断することが大切です。急変時の対応でパニックにならない為にも事前に情報を共有し、正しい対応を日頃からイメージすることで適切な対応ができるようになります。また、迅速な医療連携を成功するためには、職員同士の良質なチームワークの構築が重要です。一人ひとりが自分の役割を理解し、連携を取りながら的確に対応することが求められます。いざという時に現場で活躍できる人になりましょう。
利用者の急な体調変化に備えるためには、常に利用者に寄り添い、健康状態を把握しておくことが必要です。「いつもと違う」「何か変だな」と感じたら、悩まず情報を共有しましょう。記録し報告することで迅速な対応ができます。事前に少しでも不安を解消し、業務に臨んで頂ければと思います。
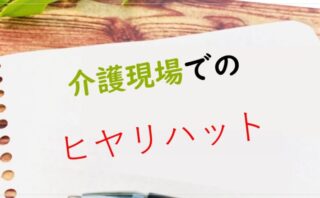
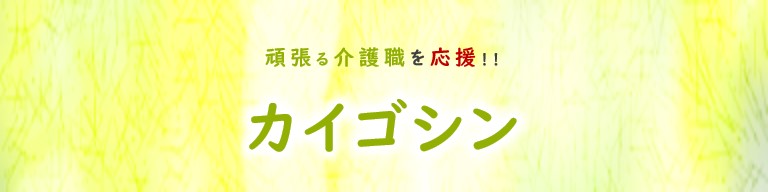
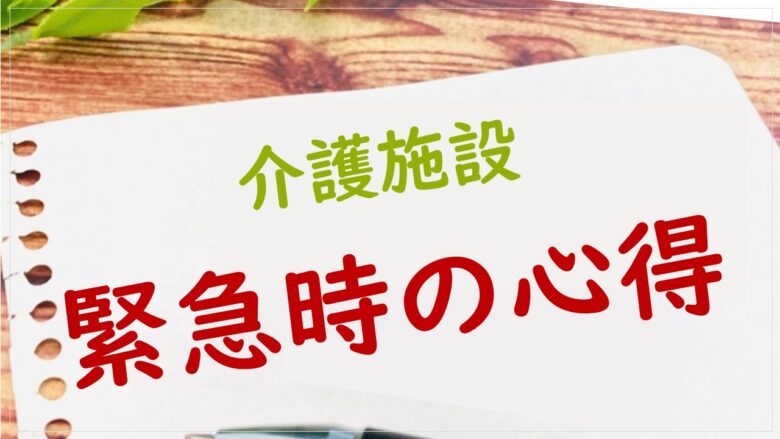
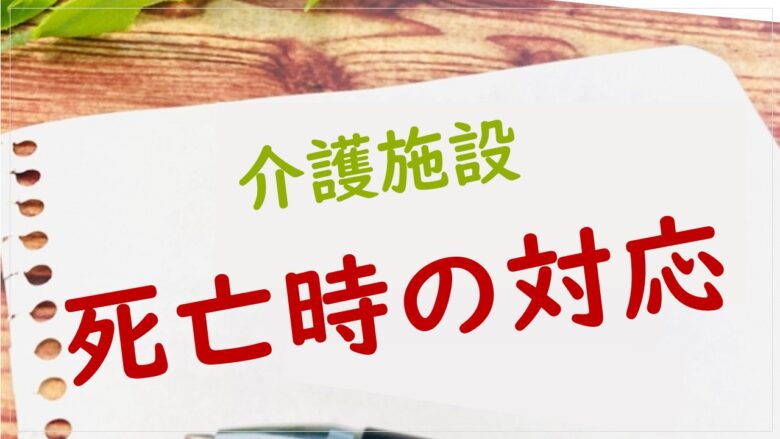
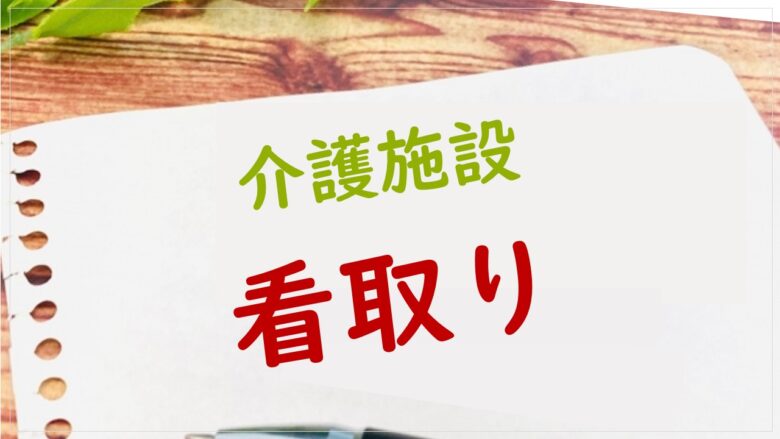
コメント